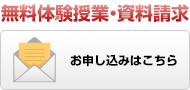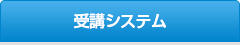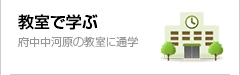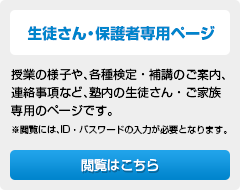月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
試験意識・・・
簡単であればあるほど、その油断からミスが発生するからだ。
だからこそ、試験で満点を取ることは素晴らしいことだといえる。
学力が同等のAくんとBくん。
学力が同等でも、試験に対する意識や取り組みで結果は全く異なる。
学力が同等なら、『極力ミスを無くすこと』
またそのための準備と練習は欠かせない。
試験終了のチャイムが鳴るまで集中して臨んで欲しい。
間もなく1学期末試験が終わる。
1学期の集大成だ。 健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月23日 15:52
| コメント(0)





試験期間中・・・
午後は自宅で翌日の試験準備だ。
間違っても 前日遅くまで頑張ったからと言って
午後はお昼寝・・・では翌日の試験結果が思いやられる。
同時に、生活のリズムが崩れてしまうので
翌日の試験中の集中力(パフォーマンス)が落ちることになる。
前述の通り、ミスを減らして得点しようと思うならば
『試験中の集中力を高める』必要がある。
帰宅後眠いならば思い切って寝てしまうほうがスッキリはする。
短時間の睡眠で対処することだ。リフレッシュ効果もある。
眠気にかまけて夜まで眠ってしまうと、
勉強時間が減るだけでなく、夜に眠れなくなってしまうから注意が必要だ。
試験に突入したら『気力と体力の勝負』
そのためには日常と変わらない生活に徹することが大切、ということだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月22日 14:46
| コメント(0)





前回試験の得点・・・
設問に難易度があったとしても『前回試験の自分の得点を上回る』
ことを最低限の目標にしよう。
ところが、前回の自分の得点を、教科毎、また合計点を覚えていない生徒は多い。
それでは今回の試験結果は期待できない。自分にとっての具体的な目標設定が曖昧になるからだ。
一方、毎回コンスタントに高得点を取る生徒は自分の実力を知っている。
当然前回の試験結果は覚えている。目標設定が明確で、前回の反省点を活かしやすくなるわけだ。
だから毎回高得点を維持できる。
今回の試験で自己記録を取りたいと思うならば、
前回試験の得点を再確認することだ。
試験準備は今まで以上に取り組んだ。
なら、試験本番は時間配分に気をつけながら、集中して臨むこと。
それだけでもミスが減り、得点できるというわけだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月21日 20:45
| コメント(0)





試験準備の仕上げ・・・
何度も練習してきた中学生も多いだろう。
試験では『覚えたことが思い出せるか、しかも短時間に・・・』が要求される。
試験直前や前日は、それでも間違えてしまう問題に集中するといい。
そうすることで、広い範囲を短時間で集中的に復習できるからだ。
さらに、見直すべき問題か否かで迷うことがあるかも知れない。
そんなときは、『もし、この問題が出題されたら・・・』と自分に問うてみよう。
やるべきか否かがはっきりする。
折角続けてきた試験準備だ。
少なくともかけた時間分の成果は欲しいところだ。
そして『他人がどう・・・』でなく、『自分はどうするべきか』
を意識することだ。
周囲の友人の言動に左右されると、良くも悪くも得点に影響するからだ。
自分のたてた学習計画を、最後までやり遂げることが
キミにとって今一番取り組むべきことだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月21日 15:44
| コメント(0)





試験準備の程度・・・
試験準備の程度に大きく影響される。
試験前は誰だって『勉強しなければ』 という気持ちが強くなる。
重い腰をあげるタイミングだ(笑)
しかし定期試験とはいえ試験範囲は広い。時間はないから
1教科あたりの勉強時間は極端に少なくなる。
日頃からある程度の勉強の下地ができていればまだ何とかなるだろうが
そうでない場合、『一夜漬け』ということになる。
覚えれば何とかなる教科ならまだしも、
解き慣れていない問題は相当苦戦することになる。当然結果は期待できない。
しかも期末試験は9教科だ。
1学期の成績が決まる試験、受験生にとっては『志望校が決まる大事な試験』だ。
『準備と練習!』
その大切さにいつ気づくことができるかで以降の成績が決まる。
特に中1生はこの1年で学んで欲しい。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月21日 05:14
| コメント(0)





試験直前・・・
それだけでも得点は上がる。
通常、平均点くらいの得点を取る生徒なら、得点は飛躍的に上がるだろう。
さて1学期末試験直前、日々の試験準備ができている生徒は
『覚える』ことより『思い出す』練習に絞ったほうがいい。
試験には時間制限があるからだ。
分かっていても時間内に解けなければ得点にはならない。
これまで解いてきた問題で、
①自分が間違えた問題
②間違えた中から、自分の間違える癖や弱点を意識しながら解く。
③試験形式で『書きながら解く』
これらに集中的に取り組むだけだ。
再度気を引き締めよう。 健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月18日 15:34
| コメント(0)





1学期末試験直前・・・
『覚えました』と答える生徒は自分の勉強に自信を持っている。
おおよそ試験の得点も高い。
一方、『だいたい・・・』 と答える生徒は多い。
だいたい、は個人差が大きい。 聞いた相手が勝手に解釈してくれるから
便利な言葉だが、実際の得点は必ずしも高いとは言えない。
部活でもなんでもそうだが、『一生懸命に頑張った分、自信が伴う』
そして相応の結果を残すものだ。
良好な成績が伴わない生徒は、すでに気持ちで負けている。
気持ちが負けているから行動できず、毎度中途半端な結果に終わるわけだ。
勉強は面倒なものだと思っているのかもしれないが、
受験までの時間的な余裕があるうちに、1度は全力で取り組むべきだ。
1度できれば2度3度、全力で取り組むことができるようになる。
自信もついて、自然と結果も伴うようになるものだ。
間もなく1学期末試験。 入塾後初めての定期試験の生徒、
今まで思うような結果を出せなかった生徒、チャンス到来だ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月17日 05:20
| コメント(0)





合否を左右する実技教科・・・
東京都では実技教科は2倍点だ。
志望校に合格したいと思うのならば、実技試験準備も怠れない。
時折、実技試験の準備なしで試験を受ける生徒もいるようだが
その分得点も低く評価も下がる。
志望校に合格するには『その分を入試当日の試験で穴埋めする』ことになる。
とはいえ、試験の上限は100点。カバーするにも限度がある。
実技試験、得意分野ならば取れるだけ得点することだ。
これが後々、入試では合否を左右するほど大きく影響する。
実技試験が良ければ、志望校合格はグンと近くなるということだ。
教科の好き嫌いもあるだろうが、志望校合格のためだ。
1学期末試験まで数日。最善を尽くそう。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月15日 16:05
| コメント(0)





問題の解き直し・・・
間違えた問題、わからない問題には✔をつける。
それだけで次の勉強内容が絞られる。
間違え問題やわからない問題は『自分の弱点』だから、
それらの問題を集中的にやり直せば良いわけだ。
この時、
『単なる見直し』で終わるか『初めて解くつもりで、覚え直してやり直すか』で結果は随分変わる。
単なる見直しは短時間で終えることができるが、定着度は低い。
一方、初回のつもりで『解き直す、覚え直す』は時間はかかるが定着度は高い。
時間的に余裕のある時期は後者でじっくりと取り組み、
時間的に余裕がなくなる試験直前は前者で『見直しと確認』 が良いだろう。
折角取り組む試験勉強だ。
『試験本番で得点する』にはどう取り組むべきか。
常に考えながら取り組んで欲しい。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月13日 14:54
| コメント(0)





1問1答式勉強
赤シート勉強法同様、効果的な勉強法だが
特に1問1答形式で試験準備をする場合は注意が必要だ。
正答率を上げようとすると、
どうしても答えを覚えてしまい、やり直し練習で直ぐに100%になるからだ。
すべてを覚えたと思えばそれ以上の勉強はしなくなるものだ。
安心しきった状態で試験に臨むも結果は変わらず。
初めての取り組みならば、前回試験よりむしろ得点は下がることもある。
1問1答は『答えを含め、問題ごと理解する』必要がある。
答えから問題が言えるようになれば得点できたはずだ。
勉強に王道なしというが、他人の勉強法の良いところどりで
楽に得点できるほど試験は甘くない。
自分なりの勉強の工夫は必要だが、
自分なりにいろいろやってみる他ない。
この試験準備をきっかけに、
日頃から『自分なりの勉強法を編み出す習慣』を身につけよう。
学校によっては期末試験前1週間。
やるべきことは多いが、再度自己記録を目指して取り組んでみよう。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年6月12日 14:37
| コメント(0)