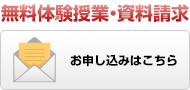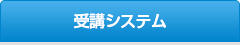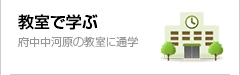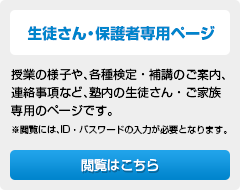月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
定期試験は勉強法を磨くチャンス・・・
そこで、少しでも自分の得点(成績)を上げるために
成績の良い友人に、彼らの『勉強法』を聞くこともあるかもしれない。
友人に勉強法を聞く時、注意したいことがある。
『友人の学力と自分の学力との差』だ。
自分の学力よりはるかに高い友人の勉強法を真似るのは難しい。
『積み上げてきたこと』 が違うからだ。
勉強法を聞くなら『自分より(高すぎず)高い得点力(成績)』の友人で
できれば複数の友人に聞くといい。
『人それぞれ勉強法は異なる』 ことを知れば、
その分、自分の勉強の取り組みに幅ができる。
そしてそれらに、自分なりの勉強の工夫を加えることができれば
いずれはそれが『自分オリジナルの勉強法』になりうる。
特に試験準備期間中は自分の勉強法改善のチャンスでもあるわけだ。
しかし勉強の試行錯誤はつづく。
学力を『高位に安定』したいなら勉強法にも変化が必要。
自分に合う自分の勉強法は、結局の所、
『自分で勉強すること』でのみ磨かれる、ということだ。
健闘を祈っている。
7C’s教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月25日 14:37
| コメント(0)





試験前の試験情報・・・
試験に出題する問題のヒントをくれたりする。
また、先生の出題傾向から、出題問題を予想することもできる。
特に定期試験前の学校の授業ではその傾向が強くなる。
そのヒント、友人たちと共有すると良い。
自動的に試験準備のモチベーション維持になるからだ。
またそれらの試験範囲の情報が、効率の良い試験勉強を可能にする。
『正確な情報収集』も得点アップには欠かせないということだ。
*ただし、情報収集に躍起になって満足し
肝心の試験勉強に集中できなくなることもあるから注意が必要。
そして親友ならもう一歩踏み込んで
試験勉強の進捗状況を聞くのもいいだろう。
『目からうろこの勉強法』が聞けるかもしれない笑
そして自分の試験勉強の参考になる部分は、積極的に取り入れることだ。
健闘を祈っている。
7C’s教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月25日 14:06
| コメント(0)





ミスの傾向を知る・・・
自分の『ミスの傾向』が浮き彫りになる。
毎度同じ問題を同じように間違えることに気づくからだ。
わかったつもりで実は分かっていないのがその理由。
『苦手だ、いやだ』と思う気持ちが、理解と記憶を阻害する。
そこをもう一歩踏み込んで考えると、突然理解することができる。
多くの中高生は、その一歩手前で諦めてしまうことが多い。
そして中途半端な状態で試験に臨むから、なかなか結果が伴わないわけだ。
試験目前だ。試験範囲には、
未だ多くの未開の地が紛れているかもしれない笑
まずは解いてみること。
自分の問題に対する理解の程度を確認することだ。解けなければ
解答解説を十分に駆使し、解法を身につけるのもいいだろう。
『自分で自分に説明しながら解いていく』 と、より理解しやすくなる。
途中式や解答を暗記するのは感心しないが
暗記するほど『繰り返し解く』ことが、良好な試験結果をもたらす。
その1問が勉強の成否を分けるかもしれない・・・
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月25日 13:04
| コメント(0)





試験本番・・・
試験ではさほど緊張しないだろう。自信がついているからだ。
いつものように、いつもの感じで試験に臨むことができる。
冷静な分、自分の『試験中の癖(ミスの傾向)』にも注意できるから
大幅にミスが減るだろう。
ただし、気をつけたいのは時間配分。
できるのに、わかるのに時間切れでは泣くに泣けない。
予想外の問題で、時間が掛かりそうなら思い切って後回しだ。
むしろ心配なのは、いつものペースで解いたら
時間が余ってしまうケース。
『試験準備中の癖(ミスの傾向)』を思い出し、答案を再点検だ。
最後の最後まで、走り抜けるつもりで試験に臨もう。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月25日 12:48
| コメント(0)





一問一答式、赤シート勉強法の注意点・・・
短時間に効率よく勉強するのには有効だ。
数回取り組めば大体の問題は解けるようになる。
しかし、弱点もある。
回数を重ねた分、『答えの羅列』で覚えてしまうこと。
また、問題の前半はよく覚えるが、後半になるほど記憶が曖昧になることだ。
一問一答式の問題が全部できたとしても
問題文の読み込みが浅くなる傾向があるので
その分、試験での正答率は下がってしまう。
『短時間で覚えたことは、短時間で忘れてしまう』 ということだ。
一問一答式や赤シートの勉強法は、
単元の全体像を知るため『最初の段階』と
短時間に復習することができる『最後の仕上げ』に使うのが良いだろう。
その間は教科書を読む。問題を解くに尽きる。
数種類の問題集の同じ単元の問題を解くことで、記憶をさらに強化できる。
連休明けには中間試験。
勉強時間を最大限確保し取り組むことだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月21日 14:58
| コメント(0)





平均80点の壁を超えるため・・・
学力はあるのになかなか400点(5科)に届かない生徒も多いだろう。
勉強方法も、試行錯誤の結果かもしれない。
目標点に届かないことが続いて、なかば諦めの心境かもしれない。
学力はあるのに得点できないケース。
多いのは試験中の集中力、注意力・・・等の欠如によるミス。
ミスがなければ高得点が取れるわけだ。
この試験では極力ミスを減らすことを意識すること。
それだけでも目標をクリアする可能性が高まる。
試験勉強中、自分のミスの傾向に気づくはずだ。(スペルミス、符号ミス、問題の読み違い・・・)
試験で同様の問題が出たら、自分のミスの傾向を思い出すこと。
そのためには自分が間違えてしまう問題に『解き慣れておく』ことだ。
特に受験生は内申点に影響する。
自分の間違える傾向を攻略することが、中間試験だけでなく
入試時にも威力を発揮する。
今試験を『入試』だと思って準備を続けよう。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月20日 16:54
| コメント(0)





中間試験6日前・・・
一度に多くの情報を、覚えようとするから覚えられない・・・
試験の度に同じことを繰り返すから
いつまで経っても得点できないわけだ。
特に勉強が苦手な学力中位以下の生徒に多い。
この流れを変えることが、学力アップの第一歩。
まずは『わかる』を『できる』にする。さらに『いつでもできる(解ける)』 レベルに
段階的に上げていくこと。
試験前1週間を切った。
今までよりも得点しようと思うなら、
得点を上げたい教科を絞り込む。
まずは得意教科の得点アップを狙うといいだろう。
学校からの課題(ワーク、プリント)を繰り返しといて覚えるといい。
『やったから、覚えたから大丈夫』 で50点。
『短時間に、正解を書き出すこと』ができて100点!
今までの勉強が『50点分の勉強』だったということだ。
ならば簡単。100点の勉強法に切り替えれば、少なくとも
今以上の得点が期待できるということだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月20日 16:07
| コメント(0)





中間試験まで7日・・・
学校の提出課題を終えた時の注意点がある。
課題を終えた途端、勉強しなくなることがあること。
試験準備のための取り組みが、
いつの間にか『課題を終えることが目標』 になってしまうからだ。
ひとは目標を達成した途端に燃え尽きる笑
だから、あくまでも目標は試験であり、課題を早めに終えるのは、
勉強のモチベーションを上げるためのきっかけ。
目標達成のための『途中経過に過ぎない』ことを自覚する必要がある。
中間試験前1週間は仕上げた課題を
『どの程度、どのくらいの時間で解けるようになるか。』にこだわること。
この問題、初めはよくわからなかった。30分かかった。
2度めの挑戦で20分。けど途中式で間違えた。
3度めは10分。問題をみたら解法が思い出せるようになった・・・と。
同じ問題でも、回数ごとにレベルを設定し取り組むことで
飽きずに、むしろ興味を持って取り組むようになる。
最初は大変だが、慣れると(解けるようになるので)楽しくなる。
楽しくなるからもう一度・・・となるわけだ。
何度やっても同じこと、と諦めてしまうか
自分を信じて継続するかで中間試験の結果は大きく変わる。
これからが本当の試験準備だ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月19日 14:38
| コメント(0)





2018年8月の模試結果・・・
全学年を通して、4月以降の偏差値が優位に上昇した。
5教科の偏差値の平均を15以上上げた生徒も多数。
しかし教室全体でみると全体の偏差値(対4月模試)の上昇は
10に届かなかった。
予想通りといえば予想通りだが、
個人的には納得できない結果の教科もあり、複雑な思いだ。
時間をかけた割には偏差値の上昇が見られなかった『英語』。
英検対策による効果も期待したが、実力は伴っても、単純なミスが多過ぎた。
数学は計算力の大幅な向上によりミスが減り、得点(偏差値)は伸びたが
苦手な単元(文章題)での問題の読み取りに不安を残した。
いずれにしても『練習量と試験慣れ、試験中の集中力』 不足!
各教科ごとに不満を挙げればキリがないが、
得点(偏差値)としては例年通りの良好な結果だ。
ミスを責めるより、生徒たちの頑張りを褒めるべきだろう。
さて頭を切り替えて中間試験に集中だ。
模試の反省が十分に活かせれば、さほど無理なくいい結果になるはずだ。
この一週間は『詰め』に徹することになる。
走る抜けるつもりで取り組もう。
健闘を祈っている。
7C’s教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月18日 14:45
| コメント(0)





2018年2学期中間試験1週間前・・・
といきたいところだったが、志望校の文化祭やら見学やらでやむなく短縮。
その分自宅学習で補って欲しいところだ。
10月上旬には英検も控えており、中学生は休む暇も無いほどだ。
より有効で効率的な時間配分が必要。
少しでも気を抜けば生活のリズムまで崩れてしまうからだ。
生活リズムが崩れれば勉強どころではない。
勉強時間の短縮は、得点に大きく影響する。
特に受験生にとっては内申点に関わる試験だからなおさらだろう。
その他、生活(勉強)リズムが崩れる原因は
①スマホ ②ゲーム ③TV・・・
1日のうち、それらの時間を家族で決めるといいだろう。
また、10月以降のTVの秋の新番組。
初回を観てしまうと、毎週観ずにいられなくなるから注意したい。
しばらくは時間との戦いになる。学習計画をたてて試験準備に臨んでほしい。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年9月18日 14:12
| コメント(0)