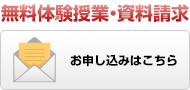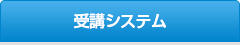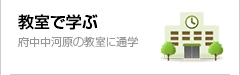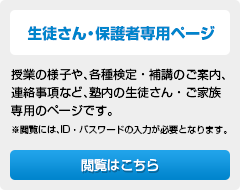月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
凡ミス発言・・・
『問題をよく読んでいなかった』という発言だ。
特に数学では問題中に多くのヒントが隠れている。
得点は、それらのヒントを正しく読み取るか否かにかかっている。
問題を正しく読み取るには、問題の『解き慣れ』が必要だ。
解き慣れておく(経験値を上げる)ことが
本番でのミスを防ぐからだ。 しかし
練習で、『解けたから、試験は大丈夫・・・』 多くの生徒がそう思う。
そう思うからそれ以上の取り組みをやめてしまう。
結果、試験までの間に『忘却』が進み、試験ではできない解けないわからない・・・。
あんなに勉強したのに、できる問題だったのに間違えた、となるわけだ。
そして、間違えの原因は『凡ミス』だと結論づけてしまう。
できる問題?をたまたま間違えただけ・・・だから『凡ミス』だと。
そうして凡ミスを毎回繰り返しているわけだ。
残念ながら
凡ミスの理由は『練習不足』だ。 学力(得点力)をつけたいならば
『凡ミスを無くす意識を持つ』ことだ。
そして2学期末試験に臨んでほしい。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月11日 14:52
| コメント(0)





『無理する』こと
中学生は大変な思いで試験準備に取り組んでいます。
『(勉強)時間がないなら、睡眠を削るしかない』 と生徒が言いました。
そんなにしてまで、と思う他の生徒もいるでしょう。確かに
無理して体調を崩したら、試験どころでは無いという見方もありますし・・・
しかし自分の限界を知るのに『無理目なチャレンジ』は必要です。
単に睡眠を削っているわけではありません。
日頃から効率の良い勉強法を模索し、改善しています。
時間管理も徹底し、学習計画表にはほとんど無駄がありません。
毎日の学習も、学校や教室の授業も真剣で
課題も部活動もきっちりこなす生徒です。 (当然成績も良い生徒です)
その生徒にとって、睡眠時間の短縮は勉強の効率化の1つの方法なわけです。
日頃から頑張っている生徒でも、試験前はそれ以上に頑張っています。
*成績が良いのは頭がいいから、だけではありません。
自分なりに考え、取り組むことで結果を得ているわけです。
さて、体を壊すほどの無理をしてはいけません。
しかし、無理を経験することで知る(得る)こともあります。
2学期末試験は、今後の学力を左右するほど大切な試験です。
過去の定期試験の反省をもとに、自分なりに考え、いい意味で『無理』
をしてみてはどうでしょう?
きっと『本当の自分の力』を感じることができますよ。
英進アカデミー まつお
(英進アカデミー)
2018年11月 9日 15:40
| コメント(0)





勉強とスマホ・・・
スマートフォンだ。
勉強の合間の休憩のつもりでも
気がつけば数十分~数時間を浪費してしまうことも多々あるようだ。
さすがに試験前は自粛の様子も伺えるが、
試験準備期間中は極力控えるべきだろう。
当然のことながら、『試験を制するには、まず自分を制すること』ということだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 9日 15:26
| コメント(0)





部活検定習い事・・・
2学期末試験準備や部活動の大会が重なっている生徒は
大変な思いをしているだろう。
しかし、それぞれの両立を果たすのも勉強の一環だ。
他の予定に試験準備の時間が削られる。
そんなハンデの中で、『どうすれば得点維持アップ』が可能かを考え
より効率よく学習するべきかを考えることになるからだ。
部活動もやっている。習い事や検定も受験する。
それでも毎回高得点をとる自分の友人は、一体どう勉強しているのか・・・
友人にできることならば、自分だってきっとできる!
そう思うことも大切だったりする。
そのために、友人や先輩方の取り組みを参考にしてみるのも良いだろう・・・
2学期の定期試験は範囲が広く難しい。
覚えればできるレベルでもないし相当の時間もかかる・・・
次から次へと襲いかかるこれらの難関を、生徒たちはどう乗り超えるか。
自分のできる範囲で構わない。全力で臨むことだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 9日 14:56
| コメント(0)





学習計画表・・・
十分活用しているだろうか。
学習計画表を上手く活用することで、勉強の無理無駄を省くことができる。
が、面倒に思っている生徒も少なくないだろう。
計画を立てる(たてかた)がよくわからないし、
作成に時間がかかるからだ。
勉強時、計画表を置き、勉強内容を記録していくことから始めてみよう。
2~3日もすれば、勉強の『偏り』が一目瞭然になる。
得意不得意の問題もあるだろうが、
(極端に多い少ない)時間配分を自覚することができる。
ついでに『どの教科、範囲』を 『いつまでに』 『どのレベルまで』
を意識して書き加えていくと、目標得点に対し、より具体的な
進捗状況を常に把握できる。
2学期末試験までおよそ1週間。
今日からやってみることだ。予想以上の成果が期待できる。
健闘を祈っている。
7C’s教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 8日 15:15
| コメント(0)





入試までの間で起こること・・・
以降の定期試験や模試結果に大きく影響するから注意が必要だ。
『現状、余裕で合格できる』 状況だとして、もっと頑張ろうと思えるならばまだ良いが
多くは現状に甘んじてしまうだろう。
入試までおよそ100日。
大丈夫だと高を括るとその間、学力は確実に落ちる。(当然入試得点は悪くなる)
それだけではない。期末試験の結果が悪いと内申点の確保が難しくなる。
入試の合否は、当日点と内申点の総合得点で決まるから
学力を落とすことと内申点減はダブルパンチだ。
一気に合否に赤信号が灯る。
さらに、期末試験や模試で『失敗した・・・』と思っている他の受験生が
志望校合格に向け、『猛烈な追い込み』をかけてくる。
この勢いは強い。ダブルパンチどころかトリプルパンチが自分にのしかかる。
・・・入試に『もう大丈夫』も『余裕』もない! ということだ。
現状の学力はどうあれ、
最終的には『志望校合格』を強く願う受験生に、勝利の女神は微笑む。
キミはどっちの受験生だ?
まずは期末試験だ。 健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 7日 14:56
| コメント(0)





勉強の無理無駄の前・・・
しかしそれは、無理無駄の経験があってのこと。
勉強不足のお子様(生徒)の場合、
まずは無理無駄を経験することから始める必要がある。
その経験が『学力の後伸び』につながるからだ。
特に中学1年生で、
中学受験を経験していない場合は早期に経験したほうが良い。
勉強時間を大幅に増やした。けど結果はあまり変わらなかった。なぜだろう?
以前より予習復習に時間をかけた。けど結果は同じ・・・なぜだろう?
毎回定期試験の度、
前回試験の反省を基に、試行錯誤しながら取り組んでみること。
これらの『なぜだろう?』経験が、
試験勉強の無理無駄を省き『自分なりの勉強法』を確立する手立てとなる。
今までの勉強方法では、いずれ限界がくるだろう。
常に改善と新たな取り組みを『継続』することで道は開けるということだ。
2学期末試験まで1週間。
部活動や検定試験と重なる生徒たちは大変な思いをするだろうが
乗り越えて欲しい。
健闘を祈っている。
7C’s教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 6日 14:11
| コメント(0)





プリント、ワーク・・・
定期試験の得点源だ。
出題される内容の多くがそれらに埋もれている笑
それらを予想できるようになるだけでも、定期試験での得点は取りやすくなる。
が、なかなかできるものではない。
提出期限ギリギリに取り組むようではまず不可能だ。
数ページから数十ページにも及ぶ量だ。計画的に早めに取り組むしかない。
早めに取り掛かる準備ができたら
次の注意点は『書き込まないこと』だ。
提出範囲までを解き終えることで満足してしまう (解き終えてからの勉強が得点になる)
からだ。
できる限り書き込まず、別のノートに解いていこう。
できなかった問題は、解けるようになるまで解き直していく。
書き込みは最後の仕上げにすること。
ほとんどの問題は解けるようになっているはずだ。
その時できない問題があれば、再度復習し直すことで理解も深まる。
地元中学では期末試験まで1週間。できることはまだまだ多い。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 5日 15:09
| コメント(0)





勉強の目標が変わってしまうと・・・
仕上げが早すぎるのも心配だ。
試験内容は提出物(ワークやプリント)から出題されることが多い。
早めに仕上げるということは、以降の試験勉強が疎かになる傾向もあるからだ。
いつの間にか、試験で結果を出す目標から
提出物を仕上げることが目標になってしまうからだ。
その目標が、試験数日前に仕上がってしまう(目標達成)
結果、試験前の大事な時に目標を無くして路頭に迷うことになる。
空いた時間を自分でコントロール(最後の詰め勉強)ができるなら良いが、
できない中学生の方が圧倒的に多いだろう。
あくまで『定期試験の得点が目標』であって
『課題を仕上げること』が目標ではないことを、確認しながら進める必要もある。
期末試験1週間前頃までは
部活動との両立を果たしながらの試験準備になる。
2学期の試験は以前より試験範囲も広く、内容も難しい。
計画的な学習に徹し、自己記録達成を果たして欲しい。
健闘を祈っている。
7C’s教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 2日 14:49
| コメント(0)





学習の取り組み、時間(期間)に余裕を・・・
なかなか目標達成できない生徒は案外多い。
目標と実力がかけ離れている場合が多いからだ。
自分の希望的観測と、周囲の目にある。自ずと目標も高くなるわけだ。
高い目標設定は大いに結構。
しかし、それに伴う学習内容と取り組み方が旧態依然としているから
結局はいつもと同程度の得点に落ち着くことになる。
勉強の取り組みを変えようとしても、気が付けばいつものやり方に戻ってしまうものだ。
そこで、勉強法(取り組み)はあえて変えずに得点を上げてみる。
例えば、確実に得点できる問題(計算、英単語、漢字)を確実にする。
出題予告のあった問題はできるようにする。
期限ぎりぎりに仕上げていた提出物を余裕をもって仕上げる・・・等々だ。
当たり前のことだが 『取り組む時間(期間)帯』 を少しだけ広げて余裕を作ること。
その分、今まで手薄にしていたことに取り組むだけだ。
得点が上がれば以降の勉強にも弾みがつく。
学力アップのきっかけになるということだ。
健闘を祈っている。
7C's教育研究所 はなぶさ
(英進アカデミー)
2018年11月 1日 15:30
| コメント(0)