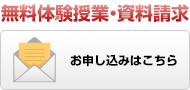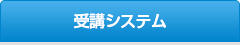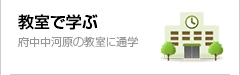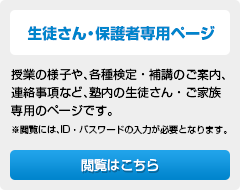月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
実技教科は合格のカギ
生徒も多いでしょう。何せ試験結果が内申点に響きますからね。
入試直前になって後悔しないようにアドバイスです。
当然のことですが
①提出物は100%出しましょう。
②授業中の態度に気をつけましょう。
それから、実技教科にも全力で取り組みましょう!
期末試験もきちんと準備して(さすがに勉強なしでの試験は厳しい)
十分な準備があれば点数も取れて、きっと評価も上がります。
5教科に時間がかかって実技教科の時間が取れない・・・
なんて事の無いように、今から5教科の準備をしておく
ことです。
受験(勉強)と同様、定期試験も重要な試験だということ
を覚えておきましょう。都立(公立)高校入学試験では、
「実技教科の内申点が、志望校合格の鍵だったりします!」
(by まつお)
(英進アカデミー)
2014年9月21日 01:56
| コメント(0)





英検に勝つ!
多いでしょう。中間試験の勉強と両立させて、ぜひ「二兎を追う」
気持ちで取り組んでください。
検定日が近いので、勉強に支障のないよう注意点だけ記します。
検定用にテキストを準備したと思います。過去問題集を使っている
生徒は答え(4択)の数字の羅列で覚えてしまっている可能性に
注意です。
試験では即答が要求されますが、まだ時間があります。
「しっかり意味が取れるか、解答解説と照らし合わせて確認作業」
リスニングは、まず「解答のページにある、放送の英文を訳しましょう」
簡単な英文しか使われていない事に気づけばあとは慣れるだけ。
何度も聞いて慣れるしかありません。また「5W1H」に気をつけて
聞き(大体文頭部分)、メモを取る練習が効果的です。
並べ替えの問題は、「実際に英作して答えを導く」練習を。
長文は、大体各段落から一つ質問されている点を意識して練習しましょう。
先に問題を読んでから、本文を読み進める方がいいでしょう。
練習した分自信がつきます!緊張やプレッシャーも少なくなります!
英進アカデミー
(英進アカデミー)
2014年9月20日 20:46
| コメント(0)





英検
申し込みした生徒も多いでしょう。
英語検定は、単に級の資格を取るだけでなく、
内申点や自己PRにもなる検定。何よりも英語の勉強に
最適な試験です。
中3終了時までの範囲が英検3級レベル。最近では早期に
準2級や2級を受験する生徒が増えています。それだけでも
英語に対するニーズが高まっていることがわかります。
近い将来の自分のために、ぜひ英語検定を活用しましょう。
次項では、英検の準備勉強について記します。
英進アカデミー
(英進アカデミー)
2014年9月20日 20:30
| コメント(0)





これまでより一歩深く・・・
を目指す方がいいだろう。もう少しで内申点を上げられるなら
なおさらだ!出来ることならば複数教科でそれを目指したい。
中間、期末の2回の試験で自己記録を達成する事を目標に、
学校の担任や、教科の先生に「自ら相談してアドバイスをもらう」
試験勉強ついでに「自己PRの練習」だ。自分の思っていることを
どう表現すれば先生方に伝えられるか、理解してもらえるか・・・
今後は「学校生活のすべてが入試につながっている!」という
意識を持って、「これまでより一歩深く考えて言動する習慣」
を身につけること。
「何事にも果敢に挑戦していくこと」が学力に大きく影響する!
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年9月19日 21:47
| コメント(0)





偏差値アップに喜べない
例え偏差値が10上がったとしてもです。「こんなに上がるほど
自分は勉強していない」という「正直な気持ち」が見え隠れします。
実際には勉強していない、でも成績(偏差値)が上がった。
単に問題との相性が良かったのか、たまたま勉強した単元が
出題されただけなのか。
確かに「一過性の成績」という場合もあるので注意も必要ですが、
結果だけをみると上がっているのは事実です。今後の学力アップの
「一つのきっかけ」として学習のアドバイスを展開する必要があります。
「納得のいかない勉強でこれだけ上がった」のなら
「納得のいく勉強ならどれだけ上がるんだろう?」と思わせる指導
(学習のアドバイス)が必要です。勉強のきっかけを掴んだのですから。
これらの生徒の学力はさらに上昇するでしょう。
7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2014年9月19日 21:28
| コメント(0)





どこから手を付ける?
30~40分で解く練習をするのも有効です。
短時間で終わらせる習慣が身につくので、実際の
試験でも余裕ができます。見直すための十分な時間
が確保できるという訳です。精神的な余裕も生まれます。
受験勉強、どこから手を付けていいのかわからない場合、
過去の模擬試験を短時間で仕上げる練習に挑戦してみましょう。
当時解けなかった問題も、案外すらすら解けるようになっているかも
しれません。当然、採点は厳密に、復習は徹底的に・・・
いくつかの過去の模擬試験(定期試験の問題でもいい)を
解いていくうちに、「あれもやった、これもやった」に気づく
と、勉強が面白いようにはかどりますよ。
さらに今後の学力は急激についてきます。受験勉強に
迷っているなら、まずはここから始めてみましょう。
7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2014年9月19日 20:38
| コメント(0)





結果をだすなら
ヒトの脳の仕組みがそうなっていますから。
数学の計算ミスはほとんどなくなりましたが、他の単元が
まだまだです。しかも、早くも夏期講習の学習内容の
記憶も曖昧になりつつあります。
だから「覚えることに集中」するしかありません。
2学期の学校の勉強、塾の宿題、受験勉強・・・
この時期多くの受験生は大忙しですが、中間試験までおよそ2週間。
1,2年時の勉強だけが受験勉強ではありませんよ。
今度の中間試験だって入試に出題される範囲ですから。
これだって入試で得点になる受験勉強です。
結果を出すなら定期試験の勉強に集中することです。
Ikawa
(英進アカデミー)
2014年9月19日 18:02
| コメント(0)





よく考えて、計画立てて
が実施される。学校行事や各種検定試験と重なる
ので大忙しだろう。学習計画通りに勉強できているだろうか?
地道に取り組む生徒と短期集中型の生徒では、
やはり取り組み方も違う。簡単に言うと、短期集中型
の生徒は勉強のツボをよく押さえている傾向が強い。
地道に取り組むタイプの生徒は、自分の能力をよく知っている。
いずれにしても「的を得ていれば必ず成績は上がる!」
夏の頑張りを改めて確かめることができるチャンスだ。
連休や祭日、土日は平日の学習スケジュールとは
異なるものを作成しておくと、勉強のリズムを維持できる。
「じっくり考えて勉強に取り組み、自己ベストを出してほしい!」
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年9月18日 23:05
| コメント(0)





『答えられて50%・・・』
ただし、使い方に注意です。
やればその問題は解けるようになります。ところが
試験では得点できない、という場合です。多くの場合、
1)その問題の雰囲気でなんとなく答えを覚えてしまう。
2)問題ごとではなく、勉強した順番で答えを覚えてしまう。
だから、質問が変わるともう答えを出せません。 よって・・・
1)一問一答の問題で勉強する場合、必ず問題中のキーワード
にマーカーします。
2)答えから、キーワードを含む問題を全部出言える(書ける)ようにすることです。
やり方を変えるだけで、本当に勉強に有効な手段となり得ます。
一問一答は『答えられて50%、答えから問題を言えて(書けて)やっと100%』
になります。単純なことですが「自分に厳しく取り組む」勉強が重要です。
英進アカデミー 7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2014年9月18日 21:41
| コメント(0)





いや、やっとスタート地点だ!
まあ、志望校に対する合格率がかなり上がったこと
を考えれば、まずまずとは言え、まだまだだろう。
第一に、「人間は一度予想以上に良い結果を出すと、次は大体失敗する!」
つまり、「妙な自信」を持ってしまう。これが「油断」となり「失敗」を招くわけだ。
第二に、「全体の結果しか見ていない講師は、必ず生徒の小さなほころびを見落とす!」
つまり、もっと上がるはずだった生徒や、もう一歩で壁を乗り越えそうな生徒
に気づかず指導を継続する。結果、徐々に生徒全体の士気は下がり、元に
戻ってしまう(学力が落ちてしまう)
中3二学期の学習内容は、多く入試に出題される。
高得点が必要な生徒なら、2学期は中間と期末試験で
自己ベストを2回続けて出す位の勢いが必要だ。
勉強にしろ仕事にしろ、「やれ!と言われてできるものではない!」
それは「脅迫」だからだ。
「自ずと勉強(仕事)に取り組める状況(環境)創り」を終始考える事が
生徒たちの更なる学力アップにつながることを肝に銘じておきたい。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年9月16日 23:49
| コメント(0)





<<前のページへ|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|次のページへ>>