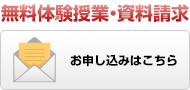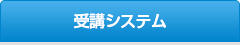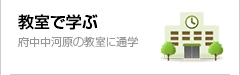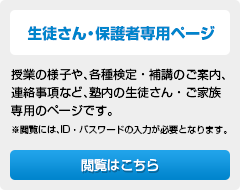月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
睡眠
試験の出来と、前日の睡眠時間を聞いて驚いた。
試験は上々だが、睡眠時間は3~4時間だったと。
これまでで一番の出来だった、という彼らの台詞は嬉しいが
教室では日々、試験前でも規則正しい生活を送るよう指導している。
頑張りは評価するが、睡眠不足は試験中の思考を鈍らせるからだ。
「志望校に合格したい」「成績を上げたい」という
意識と気力がそうさせたのだろうが、果たしてそうか?
実は学校の提出物が終わっていなくて睡眠を削ったのかもしれない。
(*実際には試験準備期間中に学校の課題はすべて消化している)
もし入試前日だったらと思うとゾッとする。どんな試験であれ
平常の状態で受験できるよう、指導の改善が必要だ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年10月10日 16:24
| コメント(0)





順番も重要
どちらを先に勉強するべきか?大学受験の高校生なら
分かるだろうが、中学生には難しいかもしれない。
食べ物の好き嫌いで、どっちから先に食べるか・・・
という質問ではない。
勉強(仕事)は苦手(嫌)な教科(仕事)をまず始めること!
苦手は後で、の発想は結局やらないで終わってしまうからだ。
得意教科を先にやると、十分勉強した気になりがちだ。
勉強はもういいだろう、と思った瞬間に苦手教科に取り組む
のが面倒になり、結果やらずじまいになるということだ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年10月10日 16:11
| コメント(0)





ライバル出現
あいつより上手くなりたい、とか早くレギュラーになりたいとか。
ライバルも自分をライバル視してくれると、この相乗効果は大です。
勉強にもライバルがいることが学力アップに大きく貢献します。
しかし部活動でも勉強でも、ただなんとなくやっている状況では
ライバルは出来ません。
ライバルは「自分と同じ目標を持って頑張るひと」にだけ現れます!
ひとは頑張っている人に魅了され、そうなりたいと思い
行動することで、いつの間にか良きライバルができます。
まだライバルのいない君、もう少し頑張ってみましょう。
きっとその存在に気づきますよ。
7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2014年10月10日 15:22
| コメント(0)





期末まで ②
「家では学校や塾でやったところ以外(1、2年の復習とか)を勉強しなさい!」
そういう親御様もいらっしゃるでしょう。入試のために一つでも
多くの問題が解けるようになってもらいたいですからね。
しかし期末試験までは学校や塾の勉強に徹するのが一番です。
この時期の勉強は「1日の勉強内容をコンパクトに、より深く」です。
中間試験同様、期末試験でも高得点を取るべく勉強することが、
結果的には入試当日の得点に結びつきます。
この時期、日々の家庭学習に1,2年時の復習を入れると
「消化不良」を起こします。なぜなら脳は新しい情報が入ると
古い情報を消去してしまう特徴があるからです。
1,2年時の復習は土日を上手に活用するのが効果的です。
塾のない日は、帰宅後から夕飯までを学校の授業の復習や課題。
夕食後に1,2年の復習をする、と分けると取り組みやすいでしょう。
公開模擬試験も11月の中旬以降に1~2回で十分です。
塾では、入試日から逆算して指導計画を立てています。当然ながら
お子様の学習進度により修正も加えます。その時期に最適な学習内容
を実施し、入試で最高の結果が残せるよう指導しています。
不安や迷いは学校や塾の担任に聞いて解決することで、ご家庭でも
お子様に最適な勉強のアドバイスができると思います。
英進アカデミー 7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2014年10月 9日 21:19
| コメント(0)





期末まで ①
塾に通っている。模試も受けている。定期試験もあるが
受験勉強もしないといけない・・・
不安は尽きないと思います。また周囲の、受験経験のある
親御様のアドバイスもあり、判断に悩むこともあるでしょう。
期末試験が終わるまでは、期末試験の範囲を何度も復習
し直すことが一番です。
①授業に集中し、問題点は授業中に解決する
②学校や塾の宿題(課題)はその日のうちに理解し覚える
③翌日は前日の学習内容をやり直す。そして当日分の復習
これだけでもその日の学習時間は十分で、就寝時間になります。
英進アカデミー 7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2014年10月 9日 20:29
| コメント(0)





試験準備は受験準備
取り組んでください。内申点云々はもちろんですが、
今回の試験範囲は入試に必出の単元です。
つまり受験勉強をしているようなもの。好都合ですね。
だからしっかりと何度も繰り返し学習し、さらに理解を
深めておきましょう。入試によく出るこの単元、
復習に時間をかけなくてもいいほどに取り組むことです。
数学だけではありません。他の教科も入試によく出る範囲です。
最善を尽くして試験に臨みましょう。
(まつお)
(英進アカデミー)
2014年10月 9日 19:55
| コメント(0)





自律訓練
が翌日の試験結果に影響することもある。
初日に失敗を感じたら、「明日頑張ろう、取り戻そう」という気持ち
になるのでまだいいが、手ごたえを感じた場合「油断が生じる」
ことがある。よって、できる問題をミスしてしまう。
意識を最後まで保つのは案外難しい。そういう意味で試験は
「自律訓練」だともいえる。「自律」ができるようになるとミスも減る。
自律を促すためには、毎回「目標」と「反省」を書き出すとこだ。
お子様が書いた文章をご覧になれば、お子様の「自律の程度」
を知ることもでき、以降のお子様の教育の指標にもなるだろう。
こどもが物事を経験する分だけ考える経験も増える。
そして「経験は次に必ず活かすこと!」を教えることも必要だろう。
試験にも、日常生活にも活かすことができる心構えだ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年10月 9日 17:58
| コメント(0)





報酬
その分だけ「燃え尽き症候群的状況」に陥ることは避けられない。
日頃から地道な勉強をしていればそうはならないとも言えない。
いずれにしても「がんばった分の報酬」は必要である。
休息日だ。無理して続けると後々行き詰まる。精一杯リフレッシュすること!
問題はそのあと、「報酬の後の勉強への切り替え」だ。
これに失敗するとずるずると過ごしてしまうことになるので注意が必要だ。
勉強に戻る(戻す)きっかけは様々だが、一つには学校や塾の宿題
だろう。これらは否応なしに勉強に戻すきっかけになる。
与えられた課題をこなすことで通常の勉強体制に戻れる。
取り掛かりは少々きついだろうが、感覚はすぐに戻るろう。
「日常生活にもメリハリをつけること!」が学力アップには欠かせない。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年10月 9日 14:45
| コメント(0)





欲張らない急がない慌てない
しかし欲を言えば、せめて他の教科も勉強して欲しい。
中学レベルの内容は、大人では一般常識にすぎないからだ。
得意教科が1科あり、他の教科が全く取れない生徒もいる。
本人は勉強しているつもりでも、気づいたら得意教科の
勉強をしていたりする。これではいつまでたっても成績は変わらない。
中3時のこの時期なら、入試では相当の苦戦が強いられる。
そうなる前に、できるだけ早期に手を打ちたいところだ。
前述のとおり、「これならば出来そう」という教科に絞った学習
が効果的だろう。
「欲張らない、急がない、慌てない!」中2中1のこの時期なら
一歩一歩前進を心がけることで自然と得点力もついてくる。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年10月 8日 20:36
| コメント(0)





得意な教科がない
満足できる得点をとったことがない。問題の解答にも
自信が持てない。単元内容の理解が浅いからだ。
早期に1教科でも得意な教科を「創る」しかない。しかし
得意な教科でさえ、1日にして成らず、だ。時間を要する。
生徒の性格を鑑み、考えを聞き、生徒の過去の生活習慣
や言動、ご家庭や学校での様子を踏まえた上で、生徒や
親御様への「得意教科創りの提案」が必要になる。
また定期試験の対策時に、教科に対する「適正」も知ることが出来る。
定期試験前の準備勉強は、必然的に5教科を学習するからだ。
「適正」がわかればその教科を集中的に指導できる。
個人差があり習得するのに時間の差は生じるが、生徒も講師も
根気よく取り組むことで、生徒は理解を深め自信をつけていく。
得意教科がない、苦手な教科だ。と思っていた生徒たち。
大変な思いで乗り越えて、いつの間にか得意教科にして、
将来その教科の専門学部学科に進学したケースも多い。
『なんとなく理科が好き・・・』でも構わない。小さなきっかけが
将来をひらくかぎになる。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2014年10月 8日 19:47
| コメント(0)





<<前のページへ|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|次のページへ>>