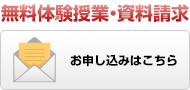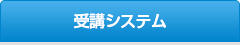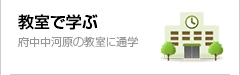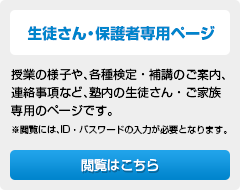月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
英語(会話)の芽・・・
1次試験の準備勉強では時々辛そうな様子の生徒たちだが、
それに比べると2次試験の準備勉強が『随分楽しそう』なのである。
これは良い傾向だ。
会話の基礎となる文章が『簡単に作れるようになった』
ということの証明に他ならないからだ。
会話の基礎になる文法は重要。
同様に『発話すること(出来ること)の喜び』を感じることができれば
英語はもっと楽しくなるに違いない。
生徒たちの『英語(会話)の芽を育む教育』が
求められる時代だ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月22日 19:54
| コメント(0)





2年二学期の重要性・・・
学校生活はさらに充実し、部活動の中心にもなっている。
とにかく目まぐるしく忙しい日々の連続だ。
学校の授業内容もまた、一段と難しくなる。
中2生は『中だるみの年』ともいう。しかし
これだけ忙しければ休みたくなるのも無理はない。
『自分を守るため』には『何かを犠牲にしなければならない』からだろう。
学校生活か、部活動か、習い事や勉強か・・・いずれか手を抜くことで
辛うじて心身のバランスを維持しているともいえる。
その子にとって『一番のストレス』が勉強であれば当然成績は落ちてくる。
部活動であれば『理由をつけてサボる』だろう。
いずれにしろ、『明確な目標の有無』が以降の日常を左右する。
学力は、一度低迷すると戻すのに相当の時間を要する。
だから毎日、最低限の勉強だけでも続け『学力維持』したい。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月22日 11:05
| コメント(0)





英検1次試験突破
全員が1次試験を突破した。よくやった、おめでとう!
『合格はあたりまえ』と前々から言ってきた。
問題は『何点で合格するかだ』と。
その点は生徒たちもしっかり理解しているのだろう。少々酷だが
合格の喜びよりは反省点の方が多いようだ。
さて、教室が得点にこだわる理由はこうだ。
合格ラインぎりぎりでは、学校の定期試験や受験での得点に
あまり反映されない。
さらに、次回受験予定の上級受験での合格が厳しくなるからだ。
本日発表と同時に、改めて2次試験の対策準備を始めた。
その先の受験と英語力アップを見越しての基礎づくりだ。
試験は11月6日、時間はあるが『期末試験試験』も近い。
明日から気を引き締めて準備に取り掛かろう。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月21日 22:18
| コメント(0)





期末理科・・・
社会同様、試験勉強は2教科分に相当する。
幼少より生き物、自然、天体が好きな生徒は多い。
よって理科2分野での得点は高い傾向がある。得点差もつきにくい。
好きな単元なら頑張れるだろう。是非満点に挑戦して欲しい。
問題は理科(1分野)だ。
物理化学が中心となる。試験には当然『計算問題』が出題される。
多くの生徒が苦手とする分野だ。しかも入試でも出題される。
この単元での得点差が合否を分けるといっても過言ではない!
苦手な生徒は早めに準備を始めるべきだろう。
最低限テキストや配布されたプリント類は100%できるようにしておこう。
上位校、工業系の高校を目指すのならば、この単元(分野)は必須だ。
時間をかけて取り組んでおきたい。
模試も含め、得点は高位安定を保ちたいところだ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月20日 16:27
| コメント(0)





期末社会・・・
地理、歴史、公民(中3生次)に分かれているからだ。
特に中2,1生は都道府県により異なるが、東京都は
地理、歴史が並行して行われる。事実上2教科と言ってもいい。
生徒によっては歴史好き、地理好きに分かれる傾向があるが
仮に得意な地理(50点満点中)で50点を取ったとしても、
苦手な歴史(50点満点中)10点しかとれなければ、合計で60点だ。
これでは内申点の確保も難しく、上位高校(都立、公立)
受験時のハンデになってしまう。
社会は『覚えれば何とかなる教科』と言われるが、
範囲が広くなる分準備にも時間をかけたい。
覚えるには時間を要するからだ。
<歴史>
①教科書を何度も読み直し、『時代の流れを掴む』
②副教材やプリント類を駆使し、全てを解けるようにする。
<地理>
歴史と同様に進める
③TVのニュースや天気予報を活用する。
入試時、『社会は得点源』だ。嫌でも『慣れること』で得点できる。
期末試験準備を早めに始めることが期末試験のポイントだ!
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月20日 16:05
| コメント(0)





『こども英語教室に学ぶこと』
毎度感心させられる事があります。
ある学年のクラスでは、教わったばかりの英語のフレーズを、
各自で配役を決め、交代しながらロールプレイングしています。
『英語は言葉。使ってこそ意味がある!』
ということを改めて感じさせます。
配役を変えながら何度も同じフレーズを繰り返すので
直ぐに上手くなります(笑)
一方、中学生はなかなか英語を話しません。
試験のための英語なわけで、正解不正解の判定が不快なのだと思います。
もっと柔軟に英語を学ぶことができれば
もっと多くの中学生が『英語は楽しい、面白い・・・』と
思えるようになると思います。
『受験英語も会話も学ぶ!』 中学部の英語の授業も日々改革です。
まつお
(英進アカデミー)
2016年10月19日 17:40
| コメント(0)





2学期末試験心得・・・
その分勉強しなくてもいい・・・とはならない!
が、心理的精神的な余裕が生じるために、
どうしても勉強量が減ってしまう傾向にある。
余裕が油断を招くからだ。
*現段階での志望校変更は、お子様の勉強意識に
大きく影響する!
そうなると無意識のうちに得点力は徐々に下がる。
親御様には、学校や塾の授業中の態度や提出物等、
お子様の、日常の小さな変化に気をつけて欲しい時期だ。
入試日までまだ時間がある。その間、新しい志望校への合格力
も下がってしまう(模試や期末試験結果は特に注意)
期末試験は
①全力で期末試験に臨むこと
②結果の善し悪しに関わらず、無闇に志望校の変更はしないこと・・・だ。
教室ではそろそろ期末試験準備を始める。
むしろ志望校のランクを『上げるつもり』で臨んで欲しい。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月19日 17:07
| コメント(0)





2学期末試験心得・・・
その分勉強しなくてもいい・・・とはならない!
が、心理的精神的な余裕が生じるために、
どうしても勉強量が減ってしまう傾向にある。
余裕が油断を招くからだ。
*現段階での志望校変更は、お子様の勉強意識に
大きく影響する!
そうなると無意識のうちに得点力は徐々に下がる。
親御様には、学校や塾の授業中の態度や提出物等、
お子様の、日常の小さな変化に気をつけて欲しい時期だ。
入試日までまだ時間がある。その間、新しい志望校への合格力
も下がってしまう(模試や期末試験結果は特に注意)
期末試験は
①全力で期末試験に臨むこと
②結果の善し悪しに関わらず、無闇に志望校の変更はしないこと・・・だ。
教室ではそろそろ期末試験準備を始める。
むしろ志望校のランクを『上げるつもり』で臨んで欲しい。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月19日 17:07
| コメント(0)





苦手な証明、実は得点源・・・
この単元、毎年入試に出題されるのだが、苦手だという中学生はかなり多い。
中3生で証明問題が苦手という生徒は、
中2,1生時に理解を曖昧にしてしまった可能性が高い。
今回、中2,1生でこの単元をしっかり身につけることで
中3生時の『苦手発言』はなくなる!
むしろ得意な単元にすることで『貴重な得点源』にもなる。
キミが中2,1生なら『苦手意識を持つ前に理解すること』だ。
証明は大きく①部分証明(カッコ内に適語を入れる)か
②全証明(すべてを記述)に分けられる。
受験生になって『証明が苦手な生徒』は中2,1生時に
①ができればOK、で済ませた生徒だ。 証明問題は
面倒でも②で練習すること!最初は解法を理解しながら書き写すと良い。
証明の流れは『パターン』だ。そのパターンを身につけることだ。
1回2回ではできるようにはならない!何度も挑戦し、自力で解ける
ようにすることだ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月18日 21:04
| コメント(0)





毎日やること、やる理由
サクサク解こうがゆっくり解こうが同じ時間だ。
取り掛かりはゆっくりでも、徐々に解答スピードを
上げていくことができれば、確実に計算力は高まる。
英単語や漢字の練習も同様だ。
問題数は少なくても、毎日必ずやるべきことだ。
計算力や英単語、漢字は長い間覚えておく必要がある。
毎日やることで『いつでも直ぐに思い出せる状態』を
維持できるからである。
その上で学校の課題や通っている学習塾の課題を消化する。
更に予習復習、受験勉強・・・となると『時間が足りない現象』が生じる。
『時間が足りない』と感じることが
『学習の効率化』へ移行するきっかけになる。
期末試験の準備前の今から始めておくと、期末試験で
その効果を実感できるかもしれない。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年10月18日 14:19
| コメント(0)





<<前のページへ|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|次のページへ>>