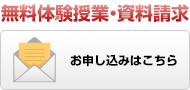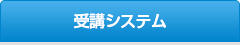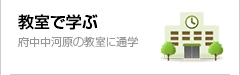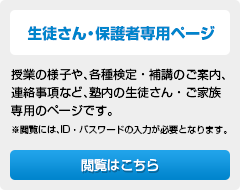月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
適量を集中的に!・・・
学習塾に通っているならば、
登塾日は塾での学習内容の復習に集中することだ。
それ以外の曜日は受験準備に集中できるだろう。
週5、6日が登塾日の場合、その日は全て塾の復習に徹すること。
この時期登塾日が多い塾は、志望校のレベルに合わせ、
入試日より逆算したスケジュールを組んでいるはずだからだ。
短時間に多くは出来ない!学習内容の定着には
『適量を集中的に!』だ。
そして過去問は週末に実施し、『厳密な時間と採点』で学力測定する。
終始得点出来ない単元(弱点)の強化に努めることだ。
やった分の得点は必ずついてくる。
これからだって逆転は可能だ。諦めずに取り組もう!
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月13日 16:12
| コメント(0)





推薦入試に過度な期待は禁物・・・
推薦での合格はラッキ-程度に考えよう。
そもそも推薦入試には内申点の高い受験生が集中する。
内申点で高得点でも『倍率に負けてしまう』こともあるからだ。
また過度の期待は、推薦入試から発表までの間、
『合否が気になって勉強に集中できなくなる!』傾向もある。
万一推薦入試に失敗した場合は一般入試を受験することになるが、
発表日までの『勉強のブランク』と『不合格のショック』が
一般入試での『気持ちのハンデ』になり、実力を発揮できないこともある。
内申点が良い受験生ならば、
今後はさらに上を目指した勉強を心がけることだ。
高校入試は人生の通過点に過ぎない!
余程合格に自信があるのならば、『入学後の自分』
を意識した勉強をすることが、入学後の余裕をもたらす。
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月12日 17:01
| コメント(0)





弱点克服が合否の要・・・
既に自分の苦手な単元に気づいているだろう。
そして解決のため最善を尽くしていると思うが、確認だ。
①志望校合格は、間違いなくその単元(弱点)の出来による。
常に弱点の確認が出来るよう、改めてノートに書き出すといいだろう。
最後の仕上げだ。徹底的に『解答スピードと正確さ』にこだわろう。
②弱点の他に注意するべきは、『平易な問題』だ。
誰もが得点出来るように出題される、いわば得点源だ。
誰もが得点できる問題でのミスも合否を左右する。
まずは徹底して②が出来るようになること。
次に①が出来るようになることだ。
最終的には『家庭学習での詰め』が大きくなる!
学校や通っている学習塾の指示には極力忠実に従おう。
そしてそれらの指導に『不満や不安』があるならば
担当の先生方にアドバイスを貰うことだ。
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月11日 14:05
| コメント(0)





入試倍率が与える影響・・・
『志望校の受験倍率が発表されること』だ。
志望校が例年通りの高倍率なら覚悟はしていただろう。
しかし意外にも低い(1倍程度や、少ないが1倍を下回る)場合、
『もう大丈夫』だと思う傾向も少なからずある。
自分では厳しい状況だ、と思っていても『周囲の声』が
油断を招く・・・『お前の志望校倍率低いな。もう大丈夫ジャン!』
言われた方はそんなつもりは無いのだが
突如として『そうかな』と思ってしまう。
すると無意識に勉強意欲がなくなることもある。
東京都立高校の場合、志望の取り下げ変更も可能だ。
入試直前の『最終倍率』が発表されるまではわからない!
最終倍率では『途端に倍率上昇』もありうるからだ。
行きたくて選んだ志望校だ。
揺るぎない気持ちで志望校合格に全力で臨んで欲しい。
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月11日 13:46
| コメント(0)





『能力開発の糸口』
今まで周囲からの評価を得られなかったばかりに自信をなくし、
やる気まで無くしてしまっている生徒も少なからずいます。
これは学力(能力)の高い低いにはあまり関係ないようにも思います。
いち早くご家族がお気づきになり、お子様に手を差し伸べることで
お子様を取り巻く状況が改善されることもあります。
そして、お子様が自分に自信が持てるようになれば、
意外な実力(能力)を発揮するかもしれません。
『もう中学生なんだからこれくらいわかるだろう?』とお思いかもしれません。
でも、まだ中学生です。中学生にはまだまだわからないことの方が多いです。
お子様が『本当はどうしたいのか?』 『何を望んでいるんか?』
実は相談したくても、できずに悩んでいるのかもしれません。
お子様が思春期真っ只中のこの時期、
親御様による、お子様への理解を深めることが
お子様が能力を発揮する最大の源だと思います。
7C's 教育研究所 英進アカデミー
(英進アカデミー)
2017年1月 8日 21:08
| コメント(0)





冬講習終了、何に気づき何を学んだか・・・
①講習後の試験の得点が上がった。しかしまだまだ足りない。
②講習前は『そんなに勉強しなくても大丈夫だ』と思っていた自分が、
今はばからしく思える。今後自分がどう取り組むべきかはっきり見えた。
③講習前は『授業の多さ』に驚いたが、あっという間に最終日を迎えた。
④家庭学習がどれだけ大事か、改めて思い知った。
⑤『宿題を終えれば勉強終わり』では意味がない。
その日の授業をいかに身につけるかが大切だと思った。
⑥家庭学習がマイペース過ぎた。わかる問題も、試験の制限時間に終われない。
家庭学習も、試験を意識した『スピードが必要』だと痛感した。
⑦手を抜いて『合格』しても達成感を得られない。何をやるにも最高の状態で臨みたい。
⑧問題集も過去問も、ただ解くだけでは意味がない。復習が大事だと思った。
⑨集中力はついた。もっと短時間で覚えるようにしたい。
⑩『もっと勉強すればよかった』と後悔だけはしたくない。
⑪この冬期講習で、どんな事にも耐える持久力や持続力がついたと思う。
⑫苦手な数学の『計算スピード』がついた。あとは正確に答えを出せるようにする。
⑬数学の文章題や英語の長文。もっと練習問題を解く必要がある。
⑭各教科の自分の弱点がはっきりわかった。入試までにできるようにしたい。
⑮改めて志望校に合格したい、何としてでも合格したいと思った。
気づきが成長を促す。また一歩、冬期講習で志望校合格に近づいた。
その気持を大切に! 勝利を信じて前進あるのみ・・・だ。
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月 8日 20:22
| コメント(0)





勉強場所・・・
通っている学習塾の自習室を利用するのも手だ。
黙々と自主的に取り組むことができる生徒ならまだ良い。
学習環境を変えることがプラスになることもあるからだ。
しかし、そうでないタイプの生徒なら、個人的にはあまり賛成しない。
①友人、知人や同級生がいると案外集中できない。
②自習は『学習計画が全て』だが、無計画な取り組みになりやすい。
③『自習室に行くことが目的』になる。
④自習室に行くことで『勉強した気持ちになる』等々・・・
確かに手の空いている講師に質問できる、という利点はあるが
折角の利点を活かしきれていないのが現状だ。
そういう意味でも『自習室を上手く活用して学力がついた』、
という生徒は案外少ないものだ。結局は自宅学習がベストだ。
まずは『自宅での学習環境の改善』から試みるといい。
机の上や机周りの雑誌やゲーム機等を整理し、勉強中の
『視界から遮断する』だけで、学習効率も上がる。
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月 7日 16:11
| コメント(0)





16冬講習最終日・・・
個人差やスタート時の学力の程度にもよるが
一生懸命に取り組んだとして、成果は早くても2週間後位からだろう。
今回の冬期講習会が2週間弱。
講習前から本格的な受験準備を始めていた受験生なら、
講習前後での得点に大なり小なり変化があるはずだ。
本日、中3受験生は受験の総合問題を受験中。
教科毎の得点、合計点の変化、講習期間中の取り組み等を
総合して、講習前後での『学力アップの程度』を測っている。
結果はまだだが、この結果による得点の変化が
以降、『入試までの総仕上げの内容』を左右する。
順調に得点が伸びれば心配はないが、
そうでない場合は早急な分析を基に修正が必要だ。
今年もあっという間の冬期講習会だった。
全員が得点アップで16冬期講習を終えることを期待する!
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月 7日 15:26
| コメント(0)





夢は身近な目標から
『将来の夢は何だ?』 『将来の夢や目標を持ちなさい!』と
周囲の大人は言います。
確かに『夢や目標を持つ中学生』はその分強い傾向があります。
しかし、イメージしにくい将来をイメージすることは、中学生には
大変なことかもしれません。
『本当はスポーツ選手や芸術家』になりたいのかもしれません。
言うと大人に否定されるので、言わないだけなのかもしれません。
だから『夢や目標を語らない子ども』を見守る姿勢も大切です。
将来のイメージがまだできないのなら、もっと現実的に
『身近なライバルや尊敬する人を目標にする』ことも有効です。
『尊敬する◯◯さんのようになるには勉強が必要だ。』
そう思える存在があれば、それが目標になり自発的に動き始めます。
『自発的に、能動的に取り組むことができる環境創り』が
結果的に『本当の学力を育む』のだと思います。
まつお
(英進アカデミー)
2017年1月 6日 21:44
| コメント(0)





『できる』と現実の落差を知る・・・
『部活動を引退した今でも、直ぐに体を動かせると思う』と。
しかし実際にやってみると、思うように体は動かないことに気づく。
しばらく体を動かすうちに、徐々に当時の感覚が蘇り、反応も良くなるが
筋肉痛は免れないだろう(笑)
出来ると思った・・・そう、 『できる感覚だけが残っている』わけだ。
ブランクの分、『確実に技術は落ちている!』
悲しいのは、『やってみるまで技術の低下を実感できない』ことだ。
これは勉強にも言えることで、
『過去に勉強して覚えたことは、いつまでも覚えている!』だから
『いつどんな試験を受けたって、いつもと同じくらいは取れる!』
そう言い切る中学生は多い。
しかし当然、学力(得点力)の低下に気づかない。
定期的な確認(試験)は必要だ。そうすることで『自分の学力(得点力)維持』
を確認できるわけだ。『忘れている』ことに気づいたらやり直せばいい!
『常にブランクを無くして取り組むこと!』を意識するだけで
学力を高めることができる! 『2017年の抱負』としてみてはどうだろう?
(by Hanabusa )
(英進アカデミー)
2017年1月 6日 20:24
| コメント(0)