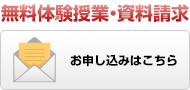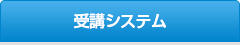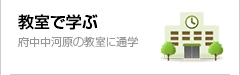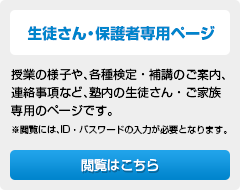月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」 > アーカイブ > 7C's教育研究所の最近のブログ記事
英進アカデミー「勝利のブログ」 7C's教育研究所の最近のブログ記事
模試の結果の活用(2度と同じ失敗はしない!)
英進アカデミーでは、毎年8月上旬(前期終了日頃)模擬試験を実施します。
この模擬試験は、昨年の夏期講習で8月31日に実施された模試です。
つまり1年先輩の卒業生の、当時の学力と「勝負」するわけです。
毎年「どのくらい頑張れたか」で「結果が大きく変わる・・・」
この状況は毎年変わりません。やはり頑張った分だけ結果が出ています。
夏期講習前半までの結果ですから、今後の頑張りによってはこの結果を
大きく上回ることは十分に可能です。(やはり「危機感」を感じることも重要)
この模試結果は有効に活用するべきです。これまでの自分の勉強の弱点を
いち早く知ることができます。
1)各教科の間違えた問題にチェックを入れる。
2)学校の教科書、参考書、塾のテキスト等を駆使して間違いを直す。
3)直しはすべて、「復習ノート」に記録する。
4)模試の解答解説があるなら、徹底的に「読んで」「理解し」「復習ノートに記録」
5)必ず、問題と復習ノートに「日付」をつけること!(5~6回見直す頃にはほぼできるようになっています)
<補足>「復習ノート」は、自分オリジナルの「参考書であり問題集!」 しっかり創って得点力アップ!!
次回以降の試験で同類の問題が出題されても「必ず得点する、できる!」状況を常に準備しておきましょう。
(by 7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年8月 8日 19:19
| コメント(0)





家での勉強
夏休みの課題は多い。学校で出された課題と塾の宿題。一体どうすればいいんだ。
そう思っている生徒もいるかと思います。いざ始めようとしても、いつの間にかただ
時間だけが過ぎていく・・・
とりあえず「10分は我慢してやること。」簡単に、これならすぐできる、と思える課題にまず
はとりかかる。
①今日塾でやった内容をやり直す。〇×つけて%を出す。100%になるまで何度も繰り返してみよう。そして
②明日の塾の課題。わからなければ、テキストにチェックをつけておく。解答解説をよく読んで、ノートに書き留めて。
それでもわからなければ明日塾で担当の先生に質問だ。家庭学習のアドバイスもついでに
してもらおう。
<結論> 「始めなければなにも始まらない、終わらない。」 (7C'教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年8月 6日 19:34
| コメント(0)





数学(算数)文章題が解けないのは・・・
数学(算数)の文章題が解けない・・・とおっしゃる親御様は多いです。
一番の理由は「問題をしっかり読めていない(理解していない)」ことにあります。
ですから周囲の大人は、「国語の読解力が足りない」とか
「もっと国語の勉強をするべきだ」と思いがちです。
確かにそうなのですが、国語力(読解力)は一朝一夕につきません。
読解力をつけるために「もっと本を読め!」と言われて読んだとしても、
文章題を解けるようになったり、国語の読解力がつくこともありません。
国語の読解力はいずれ。以下、本日は数学の文章題の解き方について簡単に述べておきます。
学校であれ塾であれ、数学の先生はまず「解き方」を説明します。
文章から式を導き出せるよう「丁寧な説明」を心がけているはずです。
ですから当然、その時点で大体の生徒は理解しているはずです。
ところが「良くわかるから復習しない(いつでもできると錯覚してしまう)」
復習しないから、文章題の言葉の意味や解き方を忘れてしまう。
つまり解き方が、いつまでたっても身につかず得点できない、文章題が解けない、
となる。(考える事が面倒な生徒にとっては、すでに問題放棄しています)
また、大抵の生徒が、文章題を解き、採点し、〇×をつけたら次の問題へ進んでしまう。
これはまるで、日替わりで部活動の種目を変えているようなもので、いつまでたっても
技術が身につかないのと似ています。(やはり一つのことにじっくり取り組んだ人は強い。)
一つの問題をじっくりと、「友達に教えてあげられる(レベル)になるまで」を目標に取り組むことです。
結局はその積み重ね。最初は時間がかかりますが、徐々に解答スピードも正確さも身に付きます。
慣れてきたら、類題問題で更に精度を高めていきます。
早ければこの夏休みで数学が得意教科になるかもしれませんよ。
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年8月 5日 17:53
| コメント(0)





五感を使って学習する
単純に「見て覚える」や「読んで覚える」勉強より、
見て、読んで、書いて、口に出して、聞いて・・・というふうに
「五感を使った学習」の方が、学習効果があります。
必要な時間も別段増えるわけではありませんし。
あまりにも単純な作業ですから、「ただ面倒くさいだけ」と思ってしまうかもしれません。
1:「見て」・・・ 視覚的に捉え、重要語句はマーカーで。記憶が映像として残りやすくなります。
2:「読んで」・・・音声を発することで、「口が覚える」
3:「書いて」・・・「手が覚える」手を動かすことで、当然脳を刺激し活性させます。
4:「口に出して」声を出すことが大事。抑揚をつけてしっかりと口を動かしましょう。
5:「聞いて」・・・必然的に声を聞くことになります。
勉強するときは、必ず1~5を同時に実行。たったそれだけです。
5倍の成果どころか、それらの相乗効果で何倍にもなって「記憶」されていきますよ。
成績の良い生徒は、無意識に実践していることが多いです。
今すぐ始めてみましょう。まずは「まねる」「試してみる」ことです。
成果は必ず、後からついてきます。
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年8月 3日 12:41
| コメント(0)





凡ミス撃退=得点アップ
講習というくらいだから授業を聴くのは当然なんですが、
やはり聴いているだけの授業では限界があります。
1、とにかく「書こう!」 それこそ講師の先生が言っていることも。
2、そして 「読もう!」 読み違いのポイントにアンダーラインを引く。
1,2年前、講師の「板書」や「説明」、「解説」までノートに書き留めていた
生徒がいました。その生徒は夏期講習だけで偏差値を「20」上げ、志望校に
合格しました。(今も高校でトップの成績を維持しています)
部活動との兼ね合いで、中3になってからの入塾でした。
当時は全くできない状態。学力も周囲の生徒と大きくかけ離れ、
授業についていくのもままならない。
そんな状況を見事に乗り越えたのです。
1、「書くこと」で、復習がしやすくなります。
2、「書くこと」で、理解が速くなります。
3、「書くこと」で、集中力が高まります。
1、「読むこと」で、読むスピードが上がります。
2、「読むこと」で、理解が速くなります。
3、「読むこと」で、「凡ミス」がなくなります。
そして、「継続」。一日も欠かすことなく、「具体的な目標」を持ってチャレンジ!
第8講座 「五感を使った学習」 (7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年8月 3日 10:00
| コメント(0)





過剰学習について
「過剰学習」という言葉があります。
良く言う「反復学習」のことです。学力をつける一番の方法です。
これは、勉強に限ったことではありません。スポーツだろうが
お稽古事だろうが同じことです。
人の記憶はおよそ1時間で半分を忘れるといいます(エビングハウスの記憶忘却曲線)。
興味のない事柄なら5分でわすれてしまうでしょう。
定期試験前日に一夜漬け。当然結果は悪く・・・
「あんなに勉強したのに得点できなかった。」
「自分は、頭が悪いんだ。」
「勉強しても意味がないよ」
そんな体験したことありませんか?
そうなんです。単にやったことを「忘れてしまっているだけ」。
それを忘れないようにすることが、勉強なんです。
忘れないように勉強? それはもう「繰り返し勉強」しかありません。
これを「過剰学習」といいます。
当然時間もかかります。しかし時間をかけた分記憶した量も多い。
結果、学力がつきます。
でも、だらだらと時間をかけるだけでは効果は半減です。
しっかりと、「テスト形式でテストだと思って」取り組むと効果も違ってきます。
「過剰学習」今日から始めましょう。
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年7月30日 21:26
| コメント(0)





勉強法(小集団授業(学習)の有効性)
グループ授業(学習)の有効性は「相乗効果」にあります。ただし、学力レベルは同じくらいが望ましい。
一人で勉強できるならそれが一番です。しかし多くの学生(生徒)にとっては苦戦する様子です。
いざ始めるとなると何をどうやって始めればいいのか、そのきっかけさえ掴めない、かわからない。
結果、気付いたら雑誌をみたり、TVを観ていたり・・・結局時間だけが過ぎていくことに・・・。
グループ授業(学習)は、リーダーを指名することです。するとおのおのに「責任感」ができます。
「責任感」が生じることで、「学習意識」が高まり「言動が活発になり」「集中力が持続」します。
ノルマを決めて、「厳しく臨む」ことが大切です。
友人達との勉強は「競争力」が生まれるので断然成果が上がります。
グループ授業を実践している学習塾は、「相乗効果」の有効性を熟知しています。
「教室」で、「講師や大人(先輩)」が「状況を把握し」「見守り」「アドバイス」を与えていく。
「最大限有効な力と時間」を引き出すことで、成果を上げています。
(7C’s教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年7月30日 14:07
| コメント(0)





夏期講習を受講してみる
学習塾の夏期講習会の総学習時間数は、通常月のおよそ3~5倍。
特に受験生で、今まで塾に通ったことがない生徒には思わぬ収穫があるかも
しれません。「効率の良い勉強方法」に「気づく」ことが多いからです。
どの塾でも、夏期講習はこれまで学校で習った内容の総まとめ(復習)を授業で
扱います。よって自分がつまずいた単元や、苦手だと思っていた単元が理解
でき、一気に学力アップする事が多々あります。
その他、自分の勉強方法の効率化や周囲の生徒達との切磋琢磨があり
「学習意識」が高まる傾向もでてきます。自発的に学習に取り組む姿勢が
身に付けば、学力アップはそう難しいことではありません。
「我流の勉強」が学力向上の妨げになることもありますから注意が必要です。
また、学習開始時期は「個別(または2~3人までの少人数」が、慣れてくると
5~6人程度の人数での学習がもっとも学習効果があります。
完全に自立学習が可能なお子様であれば、上位校受験専門の学習塾が向いて
います(人数は15~30人程度と多めですが)。
お子様に合う学習塾、通ってよかったねと言える学習塾探し。
無料体験を実施している学習塾も多いです。教室の雰囲気や指導法を知る
いい機会でもあります。
英進アカデミーでも、学習相談や進路相談を受け付けています。
ご遠慮なくご相談下さい。
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年7月19日 17:33
| コメント(0)





夏休み直前
学校から解放されて一息。でも、学校や塾の課題が山のように…
考えるだけでもうんざりしてしまいますね。
前回はなした通り、課題の終了日を7月31日に設定して、早速計画
を立てましょう。まずは自分の部屋の大掃除から。雑誌やコミック類
は、目につかないところにしまいましょう。
立てた計画表は机の前に貼って、いつでも確認できるように。
塾の課題(宿題)は復習内容がほとんどですから、
①ノートに解いていく。(日付、ページを記入)
②わからない問題には必ず✔印を付けて(ノートにも)
③わからない問題を、解答解説を熟読し再度挑戦。
*①~③が学力アップの必須条件です。
結論「夏の課題の準備=問題が「できる」か「できない」を知ること」
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年7月18日 15:04
| コメント(0)





夏休みの勉強法
夏休みの勉強法(中2,1生)前半戦
夏は暑くて部活動もあるし、課題も多くて・・・何から始めればいいのか?
結局夏休みも終わりの頃に、慌てて課題作成。
「そんな自分を今年は変えよう。」 最初は大変だけどすぐに慣れますよ。
1、課題(学校、塾)を並べてリストを作る。1日のスケジュールを立てる。終了日は7月31日とする。
2、課題のページを日数で割って、各教科の一日分を把握。「目標達成の自分ルール」を作ること。
3、1日のリズム創りを心掛ける。急な予定が入っても、課題だけは必ず終えること。
それだけの事です。自分なりに工夫して、楽しみながら達成しましょう。
「7月31日」目標達成した時の自分のイメージを思い描きながら・・・ (7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年7月14日 13:15
| コメント(0)





<<前のページへ|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|次のページへ>>
« 英進アカデミーの紹介 | メインページ | アーカイブ